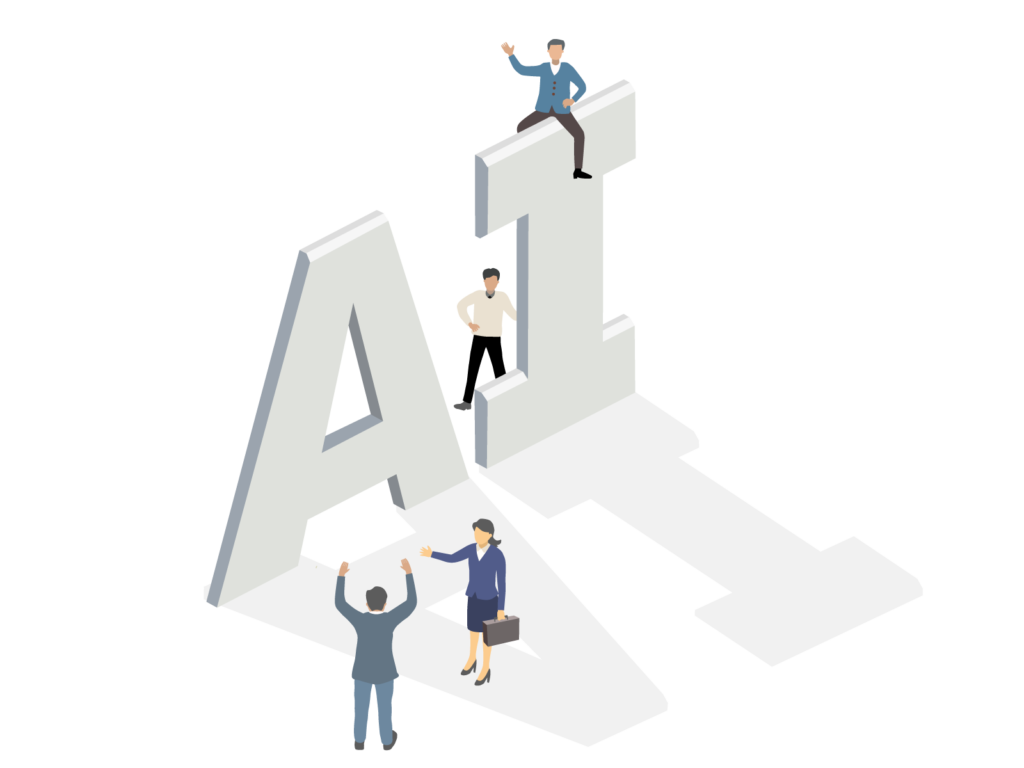
営業現場に生成AIを導入する動きは、ここ1〜2年で急速に広がりました。
商談準備、提案資料作成、メール文案作成など、効率化を目的とした活用は珍しくありません。
しかし、導入から半年、1年と経つうちに「最初は盛り上がったけど、最近あまり使われていない」という声もよく耳にします。
なぜ、せっかく導入したAIが現場で“使われなくなる”のでしょうか。原因を整理し、実践的な処方箋を提示します。
原因1:成果への直結が見えない
AIが効率化に寄与しても、それが「売上向上」や「受注率改善」という成果に繋がらない場合、現場は熱を失います。
営業マネージャーから見ても、AI活用は「便利な道具」で終わってしまい、「戦略的資産」になりません。
特に、新人は成果の伸びしろが大きくても、AIが助ける領域が限られていれば効果を感じにくい。
ベテランは自分の営業スタイルが確立されており、新しいツールを試すインセンティブが弱いのです。
■ 処方箋
AI活用のKPIを「作業時間短縮」ではなく「商談の質向上」や「案件成約率アップ」に設定します。
例えば、AIを使って提案の切り口を3案出し、それを商談で試すなど、成果に直結する場面で使う仕組みをつくることが重要です。
原因2:研修はあっても“定着の仕組み”がない
多くの企業では、AI導入時に研修を行いますが、その後のフォローが不十分です。
「研修で学んだこと」が日常業務に自然に組み込まれる仕組みがなければ、利用頻度は減っていきます。
過去に営業支援ツール導入が失敗した企業では、「また同じことになるのでは」という心理的ブレーキもかかります。
■ 処方箋
1人のAI活用リーダーを現場に置き、週1回のショートミーティングで「今週AIで試したこと」を共有する場を設けます。
成功例・失敗例をオープンに共有することで、「自分も試してみよう」という雰囲気が生まれます。
原因3:AIの役割が「便利屋」に固定されている
メール作成や議事録要約など、AIは便利ですが、それだけでは“成果ドライバー”としての存在感を持てません。
結果として、忙しい時期には「とりあえず今までのやり方でやろう」となり、AI利用が後回しになります。
■ 処方箋
AIを「便利屋」ではなく「戦略参謀」に昇格させることです。
例えば、顧客の業界ニュースを自動収集し、商談の冒頭で活用する。
あるいは過去の失注理由データをAIに分析させ、提案内容を改善するなど、“考える業務”にAIを組み込むことが必要です。
原因4:ベテランと新人の活用格差
ベテランは経験から引き出しが多く、AIをあまり必要としない一方、新人はAIに頼りすぎて提案がテンプレ化しがちです。
この格差が現場の温度差を生み、AI活用の全社的な文化が根づきにくくなります。
■ 処方箋
ベテランの知見をAIに“移植”する取り組みが有効です。
例えば、ベテラン営業の過去提案や商談メモをAIに学習させ、「〇〇業界での提案パターン」として新人が使える形にします。
こうすれば、新人は質の高い提案を短期間で再現でき、ベテランは「自分の経験が活きる」という満足感を得られます。
原因5:ツール導入が目的化している
「他社もやっているから」「上層部の意向で」という理由でAIを導入すると、現場の課題解決と直結せず、利用が定着しません。
導入時のゴール設定が曖昧なままスタートしてしまうことが多いのです。
■ 処方箋
導入前に「現場で最も困っていることは何か」を洗い出し、その課題を解決するためのユースケースを明確にします。
現場起点で設計されたAI活用は、使われ続ける確率が格段に上がります。
最後に
AIは「入れれば勝手に成果が出る魔法の道具」ではありません。
むしろ、運用設計や文化づくりの方が難易度は高いのです。
営業マネージャーが意識すべきは、“使わせる”のではなく“使いたくなる”状態を作ること。
そのためには、成果に直結する活用法を明確にし、現場で試しやすい仕組みを整え、成功体験を共有する。
このサイクルが回り始めれば、AIは一過性のブームではなく、営業現場の“勝ちパターン”として定着します。
